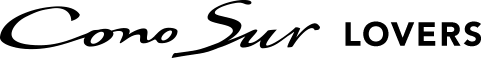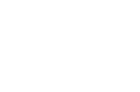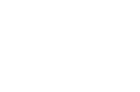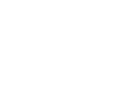2025.04.01
- 楽しみ方
さあ始めよう、ワインレッスン!
文字通り三寒四温を繰り返しながら、本格的な春の到来を待つ今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
4月は新年度がスタートし、何か始めたくなる気分になりますよね?
一説によると、1月と4月は「NHKラジオ講座」のテキストが最も売れる時期だそうです。
巷では、様々な習いごとがありますが、ワインも人気の習い事の一つとか。
ワインを嗜むことは、マナーやカルチャーを学ぶことにもつながりますので、新社会人の方にもおススメです。
そこで今回は、ワインレッスンとコノスルワインの活用について、お届けします。

■コミュニケーションツールとしてのワイン
ワインを学ぶ理由は、大きく分けて職業的なものや教養・娯楽といった趣味的な意味合いがあるでしょう。
いずれにしても、一歩ワインの世界へ足を踏み込んでみると、その奥深さや膨大な情報量に驚くかもしれません。
それだけ、ワインの歴史は古く、多くの文化と地域に根付いており、その土地の歴史や人々のストーリーが込められている証拠です。
しかし、知識や技能・技術の習得という側面以外に、ワインはコミュニケーションツールとして非常に有効であり、ワインを学ぶ大きなメリットの1つでもあります。

世界中で愛飲されているワインは、グローバルコミュニケーションツールとしての可能性が大いに期待できます。
ワインを嗜んでいると海外のレストランなどでオーダーする際も安心です。
また、海外の方をお招きする場合なども、ワインを通じてお互いの食文化や食の嗜好なども話題にしやすくなるでしょう。
さらに、ワインはビジネスシーンにおいてもスマートな印象を与えますし、幅広い年代の方と交流を持つきっかけにもなり、人脈を広げるにも有効です。

昨今のワインブームも相まって、各地で開催されるワインフェスやワイン会などのワインイベントなどで気軽にワインに触れる機会も増えています。
こうしたイベントでは参加者同士で好みを話し合ったり、他人の意見を聞いたりすることは新しい発見があり、知的好奇心をくすぐることでしょう。
それこそ、ワインを通して、ワイン仲間や生涯のパートナーに出会うといったことも・・・。
このように、ワインは嗜好的な飲み物にとどまらず、国際的なコミュニケーションの架け橋として、また、人々の心をつなぐコミュニケーションツールとして、大きな可能性を秘めています。
■注目のワインエデュケーションとは
そんな中、より専門的な知識を習得し、ワイン講師やワイン会などのキュレーター側に回る人も少なくありません。
日本では、一般社団法人ソムリエ協会(J.S.A)が主催するワインソムリエやワインエキスパート資格試験、全日本ソムリエ連盟(ANSA)が実施する検定試験などがあります。
さらに、ここ数年で受験者が急増している世界最大のワイン教育機関「Wine and Spirits Education Trust」(WSET)は、受験生が過去最大の10万8000人を記録。
各国で増加しており、日本は33%と米国を上回る伸び率を示しています。(2019年時点)※1
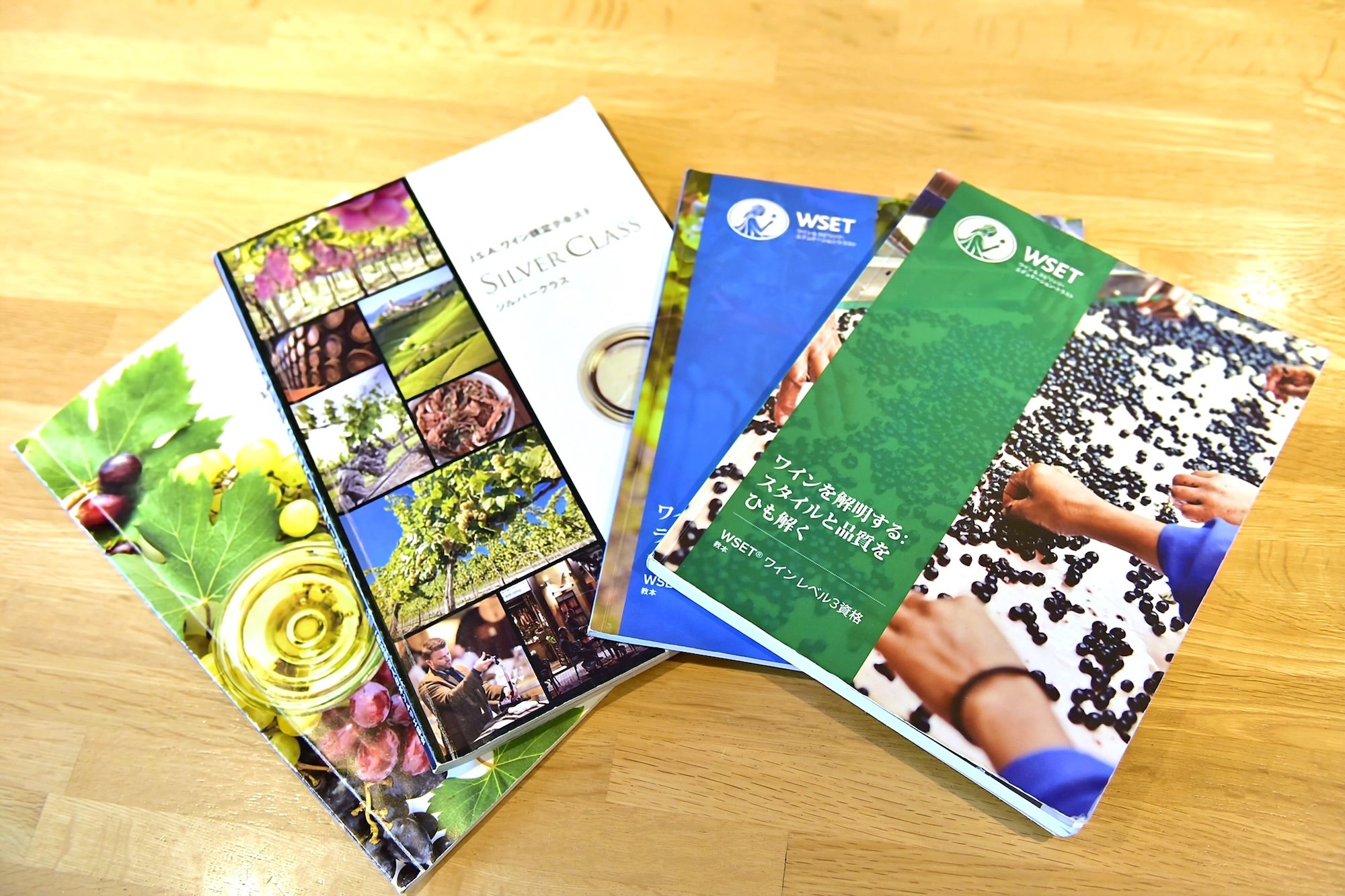
このようなワインに関する知識を深めるための教育やトレーニングを「ワインエデュケーション」と呼びます。
これは、ワインの製造過程、テイスティング技術、各地域のワインの特徴、ぶどう品種、ワインサービスや保存方法、さらにはワインとフードのペアリングなど内容は多岐に渡ります。

ワインエデュケーションは、ワインを愛好する一般の人々だけでなく、ソムリエやワイン販売業者、レストランのスタッフなどプロフェッショナルなポジションにいる方には特に重要です。
ワインを専門的に学ぶことで、提供するサービスのクオリティが向上し、スキルアップやキャリアアップにつながるためです。
こうした検定や資格試験に対する講座は、専門のワイン学校や講座があります。
また、ちょっとした教養を学ぶのであれば、カルチャースクールやワイン関連のイベントで学ぶこともできます。
無料体験講座を開催していたり、過去の受講者が体験記事などを掲載している場合がありますので、事前に調べてみるとよいでしょう。
参考:wine report 2019/08/24
■まずは、基本のワイングラスを揃える
では、ワインを学び始めるなら、何を準備すればよいのでしょうか。
それは、なんといってもワイングラスです。適切なワイングラスを用いることで、それぞれのワインや使用されているブドウ品種の特性なども的確にとらえることができます。
スクールに通うにせよ、自宅で学習するにせよ、信頼できるグラスメーカーの製品で、白ワインと赤ワイン用を合わせて2~4種類あると便利です。
手ごろな値段で購入できるものもありますので、まずはグラスメーカーのサイトをのぞいてみてください。

できれば、赤ワイン用グラスは、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローなどのボルドー系品種(左)と、ピノ・ノワールに代表されるブルゴーニュ系品種(右)のグラスがあるとベストです。

白ワイングラスは、丸い「ボウル」と呼ばれる部分が、赤ワイン用グラスよりもスリムな形状をしています。
リースリングやソーヴィニヨン・ブランなどは、上記のような形状のワイングラスが適しています。
さらに、白ワイン用のグラスで、ボウルの部分が大きめのグラスもあるとよいかもしれません。
これは樽熟成したボリューム感のあるシャルドネに適しています。
アンオークド(樽熟成をしていない)のシャルドネであれば、一般的な白ワイン用のグラスでOKです。

また、白ワインと軽めの赤ワイン兼用のグラス(左)を利用することで、準備するグラスの数を軽減することも可能です。
なお、ワイングラスは無色でプリントや細工などがないシンプルなものを選びましょう。
ワインは、味や香りだけでなく、色や輝き、粘性、清澄など、外観を見ることも大きなポイントになります。

■コノスル ワインでレッスンスタート!
ワイングラスが揃ったところで、いよいよワインの登場です。
コノスルのビシクレタシリーズは主にワインの品種毎にリリースされており、ワインレッスンにうってつけです。

<コノスル ビシクレタ レゼルバ/赤ワイン>
・レッド ブレンド
・カベルネ・ソーヴィニヨン
・ピノ・ノワール
・メルロー
・カルメネール
・シラー
・マルベック

<コノスル ビシクレタ レゼルバ/白ワイン>
・シャルドネ
・ソーヴィニヨン・ブラン
・ヴィオニエ
・リースリング
・ゲヴュルツトラミネール
<コノスル ビシクレタ レゼルバ/ロゼワイン>
・ピノ・ノワール・ロゼ
「レッド ブレンド」は名前の通り、赤ワイン用品種が5種類ブレンドされています。
それ以外は原則として単一(またはメインの使用品種85%以上)ですから、ブドウ品種の特性をつかむのにとてもよいです。
実際、ワインの資格試験対策として利用する方も多いとか。
また、すべてスクリューキャップですので、ソムリエナイフを用意する必要もありません。
コノスル ビシクレタ レゼルバ シリーズのエチケットも新しくなり、気分も刷新。
この春は、コノスルワインを上手に活用して、ワインレッスンを始めてみませんか。

この記事で紹介したワインはこちら
カベルネ・ソーヴィニョン

カベルネ・ソーヴィニョン
鮮烈なカシス、チェリー、プラムの香りに、ミントやコショウなどスパイスの香りが複雑性を与えている。エレガントでしっかりとした骨格を持つ、果実味豊かで深い味わいのワイン。
メルロー
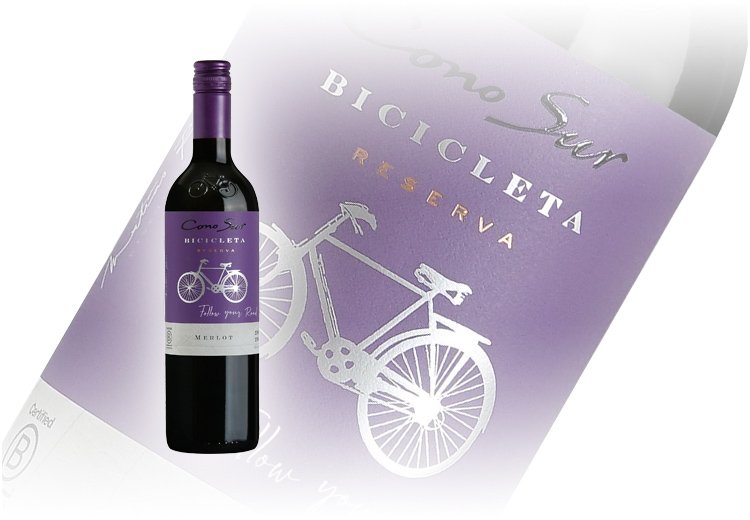
メルロー
鮮烈なラズベリーにコーヒーやチョコレートのニュアンスが複雑性を与える。滑らかで豊かなタンニンと、生き生きとした果実味が特長。洗練された余韻が楽しめる。
シャルドネ
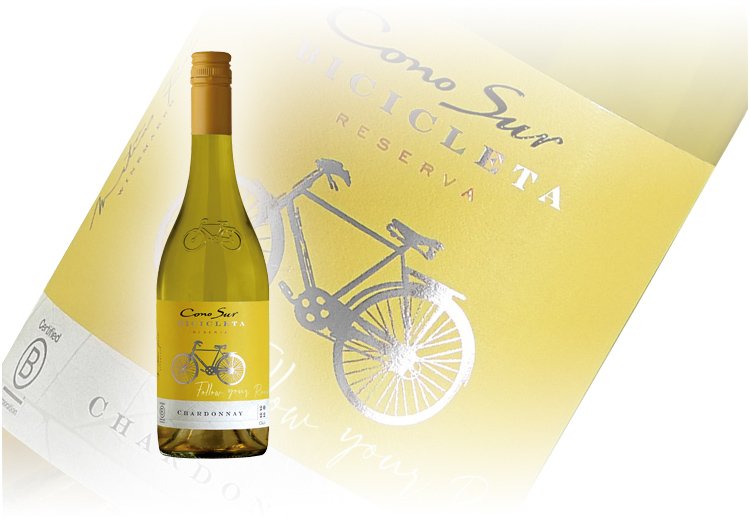
シャルドネ
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
ソーヴィニョン・ブラン

ソーヴィニョン・ブラン
柑橘系の爽やかな香りやスグリ、アプリコット、リンゴのキャンディの香りがあり、微かなハーブや緑の芝の香りが印象的。品種の個性がはっきりと現れた爽快でクリアーなタイプ。骨格がしっかりとしていて和食との相性が良い。
リースリング

リースリング
ハチミツのような香りをベースに、アプリコット、リンゴ、レモンの花、シトラスなどを感じさせるノートが複雑に絡み合っている。糖分を少々残す(7g/L)ことで、ほんのり甘く感じるスタイルに仕上げている。
この記事を書いた人

ソムリエ
たけうち あけみ
竹内 綾恵美
- (一社)日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート
- SAKURAアワード2024 審査員
料理が大好きで、国内外問わず、旅先では必ず市場を訪れる。ワインに出会い、味わいはもちろんのことワイン文化の奥深さに魅了される。
2019年にワインエキスパート取得し、ワインと食の追求に邁進する日々。