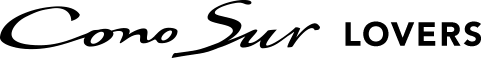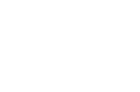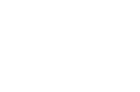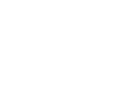2023.03.06
- チャリンコ通信
【チャリンコ通信】Vol.14 株仕立て古木の根に接いだカベルネ・ソーヴィニヨン
ノーベル文学賞歴代受賞者の中にふたりのチリ人がいる。ふたりともチリのブドウ産地の生まれだ。
ひとりはガブリエラ・ミストラル。彼女の生まれはラ・セレナからエルキ川を遡ったアンデス山間の町、ビクーニャだ。3歳の時に、そこからさらに渓谷を分け入ったアンデス山中の寒村、モンテ・グランデへ姉を頼って移住する。21歳の時に独学で教員資格を得て、全国各地で教鞭を執った。その後は外交官になり世界各地へ赴任している。14歳の時に始めた詩作を生涯にわたって続け、1945年にノーベル文学賞に輝いた。
ガブリエラ・ミストラルの生まれ育ったエルキ渓谷は、先ごろアルコワスにチリで最も標高の高い(2,200m)ブドウ畑が拓かれたことで注目されたが、じつは古くから数種類のモスカテルで造る蒸留酒ピスコの産地だった。話題のアルコワスでも長らくピスコ用ブドウを栽培していた。モンテ・グランデのすぐ隣に「ピスコ・エルキ」という名の村があって、その名のとおり、いまはここがチリ産ピスコの本拠地とされている。ところがじつはこの村、1936年までは「ラ・ウニオン」という名前だった。なぜ改名したのか。
「ピスコ」はペルーの港町の名前で、スペインの植民地時代には、ここから大きな積み荷の船が宗主国スペインに向けて出港していた。その中にペルーやチリで造ったアグアルディエンテ(蒸留酒)も含まれており、18世紀のスペイン税関はこのスピリッツを、積出港の名をとって「ピスコ」と記録していた。名前の定かでないものを積出港の名前で呼ぶのはよくあることで、たとえば米国ではスペイン産ブドウのモナストレル(ムルヴェードル)をマタロと呼んでいる。これは、このブドウの積出港がスペイン・バルセロナの北東にある港町マタロだったことに由来する。
このアグアルディエンテはペルーだけでなくチリでも造っていた。ところが18世紀にはまだ、ふたつの国はともにスペインの植民地であり、宗主国宛ての荷物は、すべていったんペルーに集められ、ピスコの港から積み出されていた。時代が下って20世紀、ヨーロッパや米国のバーでもこのスピリッツが供出され、この酒が一般に「ピスコ」と呼ばれるようになったから、ピスコのもう一方の産地チリは慌てて対応策を練ったのだった。チリ産ピスコの産地呼称と製造規定をつくってペルー産との違いを訴えるとともに、ピスコ(ペルー)の向こうを張って、チリのピスコ生産地の中央に位置する村を「ピスコ・エルキ」に改名した(ピスコの話は長くなるので、またの機会に)。
●
もうひとりのノーベル賞作家はパブロ・ネルーダだ。
ネルーダはマウレ州南端の町パラルの生まれである。パブロが3歳になるまえにネルーダ一家はアラウカニア州テムコへ引っ越した。テムコは19世紀末まで先住民マプーチェの自治下にあったことから、いまでもブドウ畑はほとんどないけれど、パラルにはスペイン植民地時代からパイスやモスカテルの畑があり、たくさんのワインを生産してきた。ネルーダの祖父母や親戚はパラルに住んでいたから、ネルーダもしばしばパラルを訪れていたようで、そのころの思い出を『ネルーダ回想録 Confieso que he Vivido』で次のように綴っている。
「わたしの曽祖父母は、バルクワインの一大産地だったパラルにブドウ畑を持っていた。わたしはパラルを訪ね、父や叔父たちからピペーニョ(自家消費用ワイン)とフィルトラド(清澄・濾過された販売用ワイン)の仕分け方を教わったことがある。いまになって思うことだが、彼らの未熟成ワイン(ピペーニョ)に対する思い入れはとても強くて、私にはとてもじゃないが受け止められない。ワインに限らず(芸術もだけれど)、いったんきれいな香りや洗練された味わいに慣れてしまうと、もはや田舎の地酒に戻ることはできないものだ」。
●
このあとネルーダの回想録は、外交官時代にパリで飲んだムートン・ロトシルトに言及している。だからもうピペーニョには戻れないというネルーダの思いは理解できる。それはさて措き、ここに書いているパラルのワイン造りは、いつの時代の様子なのだろう。ネルーダの父は1938年にテムコで亡くなったとされるから、パラルを訪ねて父やその親族からワイン造りを教わったのは、1920年代から1930年代の初めにかけてと推測できる。ネルーダ自身が20代後半から30代のころだ。
この時分のチリワイン生産量は、マウレ川以南の産地が全体の5分の4を占めていて、パラルはチリワイン主産地のひとつだった。ビクニャ・マッケンナなどのブローカーがマウレ以南の産地からバルクワインを集荷し、貨車で首都・サンティアゴやその周辺の酒屋、居酒屋、バーなどに大型容器で配達していた。当時のワイン消費量は一人当たり90リットルに達したという。大酒を食らうと酒害が目立つのは道理で、アンチ・アルコール運動はチリだけでなく国際的にも活発になっていた。米国に禁酒法が施行されたのもこのころ(1920年~1933年)のことである。
●
日本は地震大国だがチリも日本に劣らぬ地震国で、これまでもたびたび大きな地震の被害を被っている。パラルのすぐ南にチジャンという町があって、ここを震源とする大地震が1939年におきた。ワイン用ブドウの主産地を直撃したこの地震でブドウ畑と醸造所の被害は甚大だったという。ブドウ畑を復旧するにあたり、パラルに近いカウケネスの共同組合はパイスの代わりにフランスからカリニャンの樹を仕入れて植えた。
パイスはアンダルシアからカナリア諸島を経てイエズス会の宣教師が南北アメリカに持ち込んだとされている。近年、ブドウ樹のDNA解析が進み、パイスの本名はリスタン・プリエトといい、ヘレス(シェリー)のパロミノの仲間だと判明した。パロミノは小さな房の小粒のブドウで、大ぶりの房のパイスとは似ても似つかぬ姿をしている。チリのパイスは十分な降水量のある南部で、500年もの長きにわたり、常に豊産を求められてきたブドウだから、たっぷりと大きな房になってしまったのだろう。
そのうえ20世紀になると、ブドウ畑がスペイン由来のカベサ(株仕立て)から、イタリア由来のペルゴラ(棚仕立て)に変わり、1本の樹に大量の房を付けるようになったものだから、パイスの果皮の色がますます薄くなっていた。それで大地震で植え替えを余儀なくされた農家は、これを機に色の濃いサンソーやカリニャンに植え替えたのだった。

●
それから半世紀あまり。消費減退、生産過剰、政治の混乱などの紆余曲折を経て、いまやパラルのブドウ畑はわずかに250haを残すのみ。パラルの町の周囲にブドウ畑は見当たらない。ワイン用ブドウ栽培はマウレ川より北側の乾いた灌漑農業地域に移動してしまった。
そんな時、パラルから50kmほど海側(西方)に位置する非灌漑地カウケネスのブドウ畑が、突如として世の注目を浴びることになる。チリワイン業界のレジェンド、パブロ・モランデが、故郷カウケネスにポツンと残された古木・カリニャンを集めてワインを造り、それが素晴らしい出来栄えとの評判を得たからだ。
それからというもの、あっちにぽつり、こっちにぽつり、全部あわせても80haにしかならないカリニャンの古木を求めて、大手醸造所に勤めるブドウ購入担当者のカウケネス詣でが始まった。そのカリニャンの多くは、カウケネスの町の周囲と、そこから少し沿岸山地に入った辺りに打ち捨てられた状態で残っていた。日本の耕作放棄地なら、あっという間に雑草に覆われてしまうけれど、ブドウしか育たないような痩せた土地では、やせっぽちの株がしぶとく生き残っている。その多くはパイスといっしょに仕込んだ自家消費用ワインになっていたものだ。

●
コノスルもカウケネスのカリニャンには興味を持っている。だけど、わずか80haの古木・カリニャンの「争奪戦に参加するのは気が引ける」と醸造責任者のマティアス・リオスは云う。コノスルは、個性的なワインをほんの少量だけ造ることも必要だが、世界市場に向けて質量ともに安定した供給をすることも大事だと考えているからだ。
とはいえ、コノスルとしても「カウケネスの特異な風土性とそこに残る価値あるブドウの古木を大事にしたい」と思う。そして、カウケネスにはパイスの古木はカリニャンよりずっとたくさん残っている。だけど、「カウケネスのパイスでカリニャンのような品質のワインを造ることはとても難しい。大量生産の繰り返しで、パイスは大きく様変わりしてしまった」と考えるからだ。そこでマティアスは一計を案じた。
カウケネスの町から南西へ車で10分ほど移動した沿岸山地の山間に、株仕立ての古木・パイスをたくさん所有する農家を見つけた。この畑は昔ながらの有機栽培を今でも続けている。マティアスはそのパイスの古木の根に、なんとカベルネ・ソーヴィニヨンを接いだのだった。いや、カベルネとは驚いた。

●
カウケネスの海側の丘陵地は、朝方は海霧で覆われ、寒流由来の涼しい海風の吹き抜ける冷涼地である。そんな気象条件の土地に、なぜ、晩熟品種のカベルネ・ソーヴィニヨンを選んだのか。マティアスは答える。
「落ち着いて考えてごらんよ。カリニャンは暖かいラングドックのブドウで、カベルネ・ソーヴィニヨンはそこより涼しくて雨の多いボルドーのブドウだよ。ここカウケネスでは、古木のカリニャンが十分に熟しているのだから、カベルネ・ソーヴィニヨンが熟さないわけないでしょ」。確かにそのとおりだ。
私は、チリのカベルネ・ソーヴィニヨンは暖かい土地で栽培するものだと思い込んでいた。なぜなら、未熟のカベルネ・ソーヴィニヨンは青いピーマンの香りがして、それを避けるにはブドウの房に日を当てることが必要だ。日当たりなら暑いところで栽培するに限る。それで私の頭の中では、カベルネのふるさと、ボルドーの気候がすっかりお留守になっていたわけだ。
●
未熟のカベルネ・ソーヴィニヨンは青いピーマンの香りがする。ピーマンの香りの正体はメトキシピラジン(イソブチルメトキシピラジン、IBMP)という化合物。そして、カベルネ・ソーヴィニヨンの青い香りは、親品種のカベルネ・フランとソーヴィニヨン・ブランからの遺伝だ。二親とも青草のような、ピーマンのようなメトキシピラジンの香りを持っている。
この香りの化合物は、ブドウの育て方を変えることでその量をぐっと抑えることができて、ワインになった時には青さを感じないようになる。どう変えるのかと云うと、①ブドウの房と果粒を日に当てること、②一本の樹に付く房数を間引きして収穫量を抑えること、③ブドウが熟してから摘むこと。さらに、そのブドウを発酵させてからオークの小樽で少し長めに熟成すればもう完璧である。
つまりカベルネ・ソーヴィニヨンの栽培に必要な条件は、必ずしも暑い気候ではない。日の当たる時間をしっかり確保できれば良いだけだ。しかも古木の根なら一本の樹に付く房の数は少ない。それに、濃くて重いワインが好まれた時代ならまだしも、いまは薄くて旨いワイン、みずみずしくて軽快な味わいが求められるのだから、仮に青さが少し残っても、それは爽やかさ、味のアクセントとして受け入れてもらえるだろう。
●
カウケネスのカベルネ・ソーヴィニヨンだけで造るワインは、コノスルにはまだない。いまは「コノスル・オーガニック」(カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール、シラーのCCSブレンド)に使われているだけだ。このワインのテクニカルシート(ブドウの出所やワインの醸造方法を書いたもの)を見ると、2017年産からカウケネスのカベルネ・ソーヴィニヨンを使っていることがわかる。試しに近所のスーパーで、2019年産と2020年産の「コノスル・オーガニックCCSブレンド」を買って飲んでみた。
赤い果実やほのかに甘いバニラに混じって、ほんのりラズベリーのような香りがある。ワインを口に含むと、さわやかな酸味、カルメネールに由来する(と思われる)丸みや甘みとともに、かすかに感じる青さがあって全体を引き締めている。これがきっとカウケネスのカベルネの役割なのだろう。コノスル・オーガニックの味わいにちょっとした緊張感をもたらしている。

●
コノスルがカベルネ・ソーヴィニヨンを育てるカウケネスの畑のオーナーは、エルサ・ブラボという女性だ。1800年代にこの地に移住してきた家系の5代目に当たるという。コノスルと共同で栽培するブドウの他に、急斜面の小さな区画で栽培するブドウで自家用ワイン(ピペーニョ)とアグアルディエンテを造っている。
怖いもの見たさで「お宅のピペーニョを飲ませて欲しい」と申し出たら、彼女はにっこり笑って「あなたの目の前にあるでしょ。お好きにどうぞ」という。ずっと「ペプシ」の果汁飲料だと思っていた2ℓペットボトルは、なんとブラボさんちのピペーニョだった。ほんのり甘いジュースのようだがアルコール分は12%ほどあるという。きれいなワインだ。一口飲んだマティアスも「うん、よくできているね」と笑顔で太鼓判を押した。

「このピペーニョのブドウは何ですか」と尋ねたら、「あれ、なんだったっけ。たぶんポマールだよ」との答え。ポマールはブルゴーニュの銘醸村のひとつである。20世紀末、ヴァラエタルワイン(ラベルにブドウ品種名を載せたワイン)がやってくるまで、チリのボトル詰めワインは、白ワインなら「シャブリ」か「ライン」、赤ワインなら「マルゴー」「ポマール」「エルミタージュ」などの産地名で売られていた。もちろん、それぞれの原産地とは縁もゆかりもない。
ワイン造りの長い歴史のうえで、ワインが品種名で呼ばれるようになったのは、ほんのつい最近のことである。カウケネスのブドウ農家の一部では、流行りの「オレンジワイン」を「ポマール」で造っている。誰かに売りつけようというのではない。ただ内輪で飲むだけの酒である。目くじらを立てず鷹揚に受け止めてほしい。ただ、こんな答え方をしていたら「ワイン・エキスパート」にはなれない。
この記事を書いた人

ばんしょう くにお
番匠 國男
ワインライター。ワインとスピリッツの業界専門誌「WANDS」の元編集長。ワインと洋酒の取材歴37年。「日本ソムリエ協会教本」のチリとアルゼンチンの項を執筆。1993年のコノスル創業以来、ほぼ毎年、コノスルのブドウ畑と醸造所を訪問している。フットボール観戦が趣味。週末は柏レイソルの追っかけ。海外取材の際も時間が合えばスタジアムへ出かける。