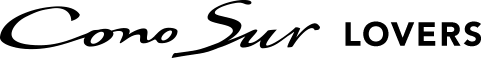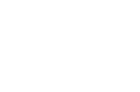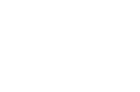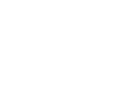2022.01.27
- チャリンコ通信
【チャリンコ通信】Vol.10 「チリワインの顔」はカベルネ・ソーヴィニヨンのはずだが。
新しい「チリの顔」が決まった。
次のチリ大統領は弱冠35歳、つい最近まで学生運動のリーダーだったガブリエル・ボリッチ・フォント下院議員。どんな政権運営をするのか、ワイン産業はどうなるのか、とんと見当がつかないようで、3月の就任式までは、誰もがじっと息を潜めるようにしてこの若い指揮官の動向を見守っている。
というのも、ピノチェト軍事政権が民政移管した1990年以降の30数年、チリの政権は中道左派と中道右派がかわりばんこで担ってきたから、政権が交代しても大概のことは予測ができた。ところが今回ばかりは、1970年のアジェンデ政権誕生に匹敵するような大きな変化があるかもしれない。あの時は、ブドウ畑をそっくり国に召し上げられてしまったワイナリーもあったけれど、はたしてこんどはそんな大騒動がありやなしや。ただ、選挙戦の最中からボリッチさんは、TPPなどチリがすでに署名している貿易協定の見直しを主張しているようだから、チリワインの消費市場にも政権交代の影響が及ぶのかもしれない。
●
過去3回にわたってコノスルとチリワイン産業の地球温暖化防止に向けた対応策を紹介してきたが、話題をいったんワインとブドウに戻して、今回は「チリワインの顔」ともいうべきカベルネ・ソーヴィニヨンに纏わる話をしよう。
チリのブドウ畑でいま、一番多く栽培されているブドウはカベルネ・ソーヴィニヨンである。この原稿を書くに当たって、まずは世界中のカベルネ・ソーヴィニヨンの栽培面積を調べてみようと思い、資料に当たると、なんとチリはフランスに次いで世界第2位の「カベルネ栽培国」だった。
まぁ、カベルネ・ソーヴィニヨンはボルドー原産のブドウだからフランスが栽培面積世界一と云うのはわかるけれど、カリフォルニア(米国)やオーストラリアよりもチリの栽培面積が広いとは。これは意外だった。さらに、それぞれの国で栽培している全てのワイン用ブドウに占めるカベルネ・ソーヴィニヨンの割合をみると、チリが断然トップで、およそ3割を占めている。
●
カベルネ・ソーヴィニヨンの栽培面積は、ナパヴァレーを擁する米国の方が、チリよりずっと広いだろうと私は思い込んでいた。というのは、今日ただいまのようにワインがブドウ品種名で語られるようになったきっかけは、1970年代のナパに新植されたカベルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネにあったからだ。
1976年、米国独立200年を記念して、フランスのパリで米仏両国ワインを目隠しで比較試飲し、その優劣を決めるという催しがあった。赤ワインはボルドーの有名シャトーのもので、米国産はそれに合わせてカリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンのワインが充てられた。審査したのは当代フランス一流のシェフ、醸造家、ワイン評論家たちだったが、結果は、ボルドーの名だたるシャトーをすべて抑えて、ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンが勝った。スタッグス・リープ・ワイン・セラーズという若い醸造所が、その3年前に植えたばかりのカベルネ・ソーヴィニヨンを初仕込みしたものだった。
●
これは今なら世界のワイン産業を揺るがすような大ニュースだけれど、当時はそれほど大きな話題になっていない。まして、まだナイアガラやコンコードで甘味ブドウ酒を造っていた日本は知る由もなかった。このイベントが日本のワイン業界にも知られるようになったのは、比較試飲会から20年後の1996年。第1位になったカリフォルニアワインのボトルが、スミソニアン博物館のコレクションに採用されたことがきっかけだったと私は記憶している。あるいは多くの人はそれ以前から知ってはいたけれど口にせず、20年遅れでようやく私が知ったと云うことだったのかもしれない。
いずれにせよ、カリフォルニアワイン産業がこの比較試飲の結果に自信を持ち、以降、カベルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネの植栽面積を大幅に広げ、ラベルに品種名を表示したヴァラエタルワイン造りに邁進したことは歴史が示すところである。それからというもの、ヴァラエタルワインは世界中の産地から消費地まで、すべてのワインシーンを巻き込んで、いまではワインをブドウ品種名で語ることが普通になってしまった。
●
そのヴァラエタルワインは、1980年代も半ばになって、ようやくチリにもやってきた。まことに遅れ馳せである。ところがそれからのチリワイン産業の対応は速かった。ふつうワイン用ブドウ樹は植えてから最短でも3年経たないとワインにできないのだが、チリでは1年も待つことなく即座にこのカベルネ・ソーヴィニヨンのワイン造りに対応することができた。
というのも、このブドウ品種は19世紀半ばにはボルドーからチリのマイポに移植されていたもので、チリには樹齢の高いものも含めてカベルネ・ソーヴィニヨンがたっぷり揃っていたのである。しかもチリのブドウ畑には、フィロキセラ(ブドウ根アブラムシ)の被害が無かったので、19世紀半ばのボルドーで栽培されていたそのままの状態がチリのマイポにきれいに保存されていた。このことは自然の恵みの有難さと云うよりも、100年の歳月を越えて栽培家の祖父母や曾祖父母から届いた贈りものと言えるだろう。
ブドウ畑にカベルネ・ソーヴィニヨンはたくさんあった。大急ぎで揃えたのはワイン造りの設備である。それまでチリの赤ワイン造りは、ラウリというチリ中部に自生するブナ(ナンキョクブナ)の木で大きな桶を作り、その桶で発酵させ、そのまましばらくそこで貯蔵していた。ラウリの大桶を解体し、その代わりに発酵の際の温度制御装置の付いたステンレス鋼のタンクを据え付けた。そして小さなオーク樽(容量ボトル300本分)をフランスと米国から購入して、これでワインを熟成させた。
●
醸造設備は俄か造りだったけれど、できあがったカベルネ・ソーヴィニヨンの品質は高く、英国でも米国でもすぐに評価され、あっという間に輸出量はうなぎのぼり。日本でも「チリカベ」の愛称で大そう売れた。ことに1997年暮れから1998年初めにかけての赤ワインをめぐる大騒ぎの時に、安くてポリフェノールが多くほんのり甘い飲み口の「チリカベ」はその主役を演じ、日本のワイン市場に一大ブームを起こした。
ところで、このごろは20世紀末の「赤ワインブーム」とか「チリカベ」と云ってもピンとこない世代が増えたようで、ワインセミナーなどでそんな話をしても反応がとても薄い。そりゃそうだ。だってもう25年も前のことだから、赤ワインブームをリアルタイムで体験した方々は、もっとも若い人でもすでに45歳を超えている。せっかくだから、どんなことがあったのかを簡単に書き留めておこう。
それは、とあるテレビ番組が「赤ワインに含まれるポリフェノールは血管系疾患の予防に効果がある」と伝えたことがきっかけだった。これを視た普段はワインを飲まない人々が、身体にいいのなら飲んでみようと赤ワインを買いに酒屋へ出向く。1997年秋のボージョレ・ヌーヴォー販売解禁の頃から赤ワインが売れ出して、年末にはあちこちの売り場で欠品する騒ぎに。
そしてついに1998年の正月。休みあけの酒売り場の赤ワイン棚は、どこもかしこもスッカラカンに。業界は大慌て。八方手を尽くして調達したが、赤ワインの供給が潤沢になった春頃にはすでにブームの熱が冷めており、店頭も倉庫も大量の赤ワイン在庫の山になった。ちなみに1998年のワイン輸入量は前年の2.4倍、なかでもチリワインは5倍に跳ね上がった。この年に輸入されたワインの総量は「3億3,252万本」で日本ワイン史上最大。あれから25年が経ち、日本にもワインはずいぶん普及したように見えるが、未だに1998年の記録は破られていない。
●

話しが逸れてしまった。カベルネ・ソーヴィニヨンに戻そう。
「チリカベ」が日本に紹介されたころ、色が濃くてやや甘くポリフェノールたっぷりという評判とともに、「チリカベはピーマンの香りのするワイン」という指摘もあった。ピーマンの香りの正体はメトキシピラジン(正確にはイソブチルメトキシピラジン、略してIBMPというそうだ)という化合物で、これはカルメネールの話の時にも触れている。カベルネ・ソーヴィニヨンの親品種はカベルネ・フランとソーヴィニヨン・ブランで、二親とも青草のような、あるいはピーマンのようなメトキシピラジン由来の青い香りを持っているから、これは間違いなく親から遺伝したものである。
この香りの化合物は、ブドウの育て方を変えることでその量をぐっと抑えることができて、ワインになった時には青さを感じないようになる。どう変えるのかと云うと、①ブドウの房と果粒をなるだけ陽に当てること、②一本の樹に付く房数を間引きして収穫量を抑えること、③ブドウがよく熟してから摘むこと。さらに、そのブドウを発酵させてからオークの小樽で少し長めに熟成すればもう完璧である。
「コノスル・20バレル・カベルネ・ソーヴィニヨン」は、そうした栽培と醸造の工夫の積み重ねの末に誕生したワインである。
●

サンティアゴ市の中心部から南へおよそ15kmにマイポ川が流れている。この川はアンデス山脈の雪解水を集めて西へと流れ、海辺のリゾート、サント・ドミンゴで太平洋に注ぐ。上流部(アルト・マイポ)の河川敷から一段高くなった河岸段丘がチリのカベルネ・ソーヴィニヨンの主産地だ。
アンデスの麓、マイポ川南岸にピルケという小さな町がある。先住民が川の上流から水を引いて灌漑の基礎をつくり、18世紀にはそれを改良した用水路ができて、この地に耕作地が広がった。いまでも車でピルケの田舎道を走ると、マイポ川の干上がる夏でも、その用水路を伝う水音が聞こえてくる。
19世紀半ば、アタカマ鉱山で大儲けした人々の愉しみは、大型蒸気船で大西洋を渡り、パリやロンドンで物見遊山することだった。そこで飲んだボルドーワインがいたく気に入ったので、サンティアゴへの帰路、ボルドーのブドウ樹を携え、それをピルケの畑に植えたのである。さらにボルドーのシャトーを模したカソナ(城館)を建て、大きな庭園を築き、家具調度はフランスから買い入れた。当時のピルケにはサンテミリヨンの趣があったという。
●

19世紀後半に拓いたピルケのブドウ畑のひとつがピルケ・ビエホで「コノスル・20バレル・カベルネ・ソーヴィニヨン」は、そのブドウで造っている。
河岸段丘は、川の運んだ大小の丸い石ころだらけの地層の上に、粒子の細かい粘土が積もってできている。日中の日差しは強く乾燥した日々が続くけれど、先達の築いた灌漑水路のおかげで土は適度の水分を保っている。夕方になるとアンデスから吹き下ろす冷気が、乾いて暖まった畑の空気とブドウ樹を冷ますから、ここのカベルネ・ソーヴィニヨンはゆっくりと熟す。醸造しても新鮮な果実の香りときれいな酸味を逃さない。そして、ここ20数年の新たな栽培経験がマイポのカベルネの青っぽさをすっかり消している。
「コノスル・20バレル・カベルネ・ソーヴィニヨン」はよくできた本当においしいワインで、ボルドー・グランクリュに比肩すると私は思う。1976年のパリの出来事のように、先行情報を遮断し目隠しで比べると、その実力がよく分かるはずだ。
このごろは薄くて旨いワインばかりが持て囃されるけれど、旨さと酸味のバランスのとれた濃いめのワインも捨てたもんじゃない。21世紀のチリは海のそばの冷涼地や穏やかな気候の南部に新しいブドウ畑を拓くことが多かったので、ともすればそこばかり目が行きがちだ。
けれども忘れてもらっては困る。「チリワインの顔」は、19世紀半ばからずっとアンデスの水と土と冷気に育まれてきた生粋のカベルネ・ソーヴィニヨンであることを。
この記事を書いた人

ばんしょう くにお
番匠 國男
ワインライター。ワインとスピリッツの業界専門誌「WANDS」の元編集長。ワインと洋酒の取材歴37年。「日本ソムリエ協会教本」のチリとアルゼンチンの項を執筆。1993年のコノスル創業以来、ほぼ毎年、コノスルのブドウ畑と醸造所を訪問している。フットボール観戦が趣味。週末は柏レイソルの追っかけ。海外取材の際も時間が合えばスタジアムへ出かける。