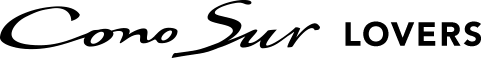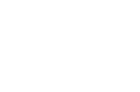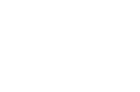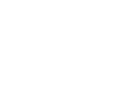2021.09.21
- チャリンコ通信
【チャリンコ通信】Vol.8 ブドウ畑の生態系を守るコノスルの取り組み
不要不急の外出自粛生活が始まってはや一年半。
この間、昼夜を分かたず働いていただいた医療・介護関係のみなさまには、まったく頭が上がりません。ありがとうございます。
自粛生活の過ごし方のひとつは、近くの田んぼ道を歩くこと。おかげで稲作の一年をつぶさに観察できた。その代わりブドウ畑はすっかり見てないけれど。稲の成長サイクルを見ていると、素人でも幾つか分かったことがある。
ひとつはコブハクチョウの狼藉だ。コブハクチョウは外来種で、本来は渡り鳥のはずだが、沼には餌がたっぷりあるもんだから、渡りをせずに居ついてしまった。田植えの終わった頃合いを見て、沼から徒党を組んで用水路を伝い、田んぼに侵入して苗を食い荒らす。農家はたまったもんじゃない。
もうひとつは、収穫前の稲がみな倒れてしまう倒伏(とうふく)という現象。強い台風の後ならいざ知らず、大した風も雨もないのに軒並み稲が倒れてしまう。それが、あちこちに広がっている。ちょうど居合わせた農家さんに聞くと、「土が悪くて根がしっかり張れてなかったり、窒素過多で稈(かん、稲の茎の部分でのちに藁になるところ)が弱ったりしてるんだろう」とのこと。これって、どっちもこの地域の生態系が壊れてるとか、壊れかけてるってことだよね。
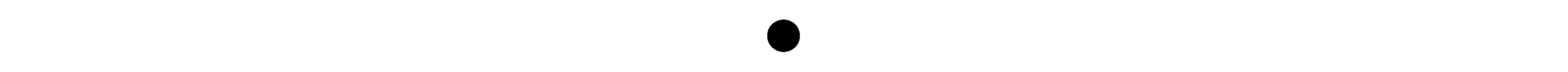
私の散歩道は、元はとても大きな沼を干拓してできた田んぼに沿った農道だ。かつての沼にはたくさんの生物がいて、沼の岸から近くの里山へと生き物の往来する道が繋がっていたはずだ。人はその間の猫の額ほどの小さな土地を耕し、あるものは沼の魚を捕って生きていた。近年、その沼をそっくり埋め立てて新田を拓く事業があって、見渡す限り一面の田んぼという景観が生まれた。これが東京ドーム何個分に当たるのかは知らないけれど。
里山と土と水、そしてそこに棲む生物の相互の関りはとても複雑なものだ。そして人はその複雑な仕組みから自然の恵みを受けてきた。それを人の都合で、あちこちでバチバチと断ち切ったら、そりゃあ何か障りが起こるはずだ。その障りが積もり積もって、いまでは地球規模の問題になっている。なかでも厄介なのは大気中に溜まった二酸化炭素などの温室効果ガスというやつ。このガスが熱を吸って大気が温まり天変地異を引き起こしている。
生態系(エコシステム)の回復と保全という取り組みは、このあたりで何とかその障りを食い止めて、豊かな地球を子や孫やその次の代に渡そうというものだ。でも、そっくり太古の昔のままに戻すことなんてもうできっこない。できるところから手を付けて、あるいは肝になるところに手を入れて何とか修復しようという取り組みだ。
それなら、目の前にある大沼を干拓した田んぼで起きている障りの原因は何だろう。それはどうやら、この田んぼが「見渡す限り一面」に広がっていて、そこで農薬を散布しながら稲の単作を繰り返していることにあるらしい。生態系の回復にはこのような単作農業を止め、複数の植物を混植するなどして、少しずつ少しずつ、かつての生態系を取り戻すようにする必要があるという。
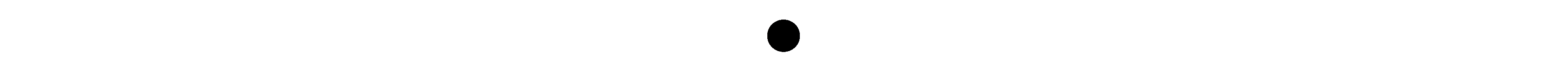
気象の変化には誰もが気づくけれど、農地の生態系が壊れかけていることは都市生活者にはなかなか伝わりにくい。ブドウ農業の場合は消費の最終形態がボトルに詰めたワインだからなおさらのこと。ましてチリのコノスルのように地球の裏側にあるブドウ畑のことなど気に掛けるはずもない。それで今回は、コノスルのブドウ畑とその周囲の生態系保全の取り組みの話。ふぅ、やっと本題に辿り着いた(いつものことだけど、前振りが長すぎる)。
チリのセントラルヴァレーに広がる景観は、「見渡す限り一面」のブドウ畑で、干拓で新田開発された日本の田んぼのそれと似ている。パンアメリカン・ハイウェイを走る車からの眺めは、はるか遠くに霞んで見える山裾まで、そっくりみんなブドウの樹列で覆われている。そう云えば、1990年代の初めに、カリフォルニアのセントラルヴァレーで見た景観はこんなもんじゃなかった。四方八方十六方、地平線の彼方まで、なにしろずっとブドウの樹が並んでいたっけ。
そのブドウ畑は、畝間の雑草をきれいに取り除き、ブドウ樹の背丈と葉の広がりをきっちり整えて、樹列がまるで軍隊のように一部の隙もなくきれいに列を成していた。そんな整然とした広大な畑の景観こそがすばらしいと思っていた時期が私にはあった。そして、あろうことか、それができない者を駄農と見做していたのである(なんと愚かな!)。
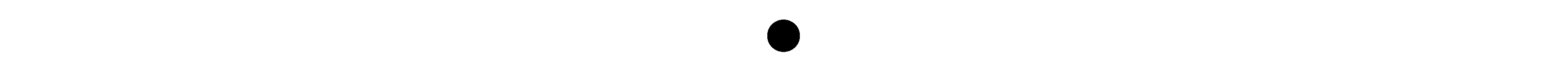
ブドウ栽培は昔ながらの有機農法から、大量の収穫を実現するために合成肥料と農薬を使った慣行農法に切り替わった。この農法のおかげで1960年代以降、世界中のブドウの生産量が飛躍的に増えたのだった。チリも同様だった。
ところが21世紀を目前にして、チリのブドウ畑には、壮大できれいな景観に不都合が生まれていた。ブドウ畑の土がカチカチに硬くなり、樹の周りには虫も蝶もいなくなった、ブドウ樹には葉が茂りすぎるという問題が生じた。土と樹に関することだけでなく、畑仕事をする人からも頭痛や肌のかゆみなどの不調を訴えるものが出てきた。これは、土に定期的に合成肥料を与え、除菌剤や除草剤など農薬を使って樹を防除する農法が原因ではないか。だって、合成肥料や農薬のなかった祖父母の時代にはこんなことは無かったのだから。
ところで、合成肥料は「化学肥料」ともよばれるから、殺虫剤や除草剤のように何か強い薬物でも混ぜているかのように思われ勝ちだが、じつは窒素、燐酸、加里といった自然の肥料を合成したもので、原料はまったく自然のものである。ただ、たとえば窒素の場合、有機肥料の窒素をブドウの根が吸収するためには土中のバクテリアが介在してかたちを変える必要があるけれど、合成肥料の窒素はバクテリア要らずで、はじめから根がそのまま吸収できるかたちになっている。だから合成肥料を使い続けると土中に微生物が居なくなって土がカチカチに硬くなる。それで、有機肥料に戻して土中の微生物を復活させ、フカフカの土を取り戻そうというわけだ。
1990年代後半になると、チリのブドウ畑のあちこちで「インテグレーテッド農法」という新しい言葉を耳にするようになった。これは曖昧な言葉だけれど、畑で実践している仕事から類推すると、すぐには有機農法に戻せないから、有機と慣行農法を都合よく「統合」した方法を採用して徐々に有機農法に戻そう。つまり、慣行から有機へ戻すための過渡的な農法のように見えた。
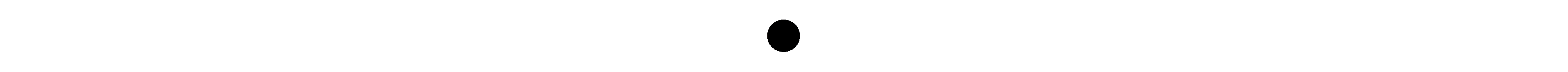
コノスルは逸早く統合農法を実践し、そこから次々と有機栽培に転換して、そのブドウで造ったオーガニックワインを世界中に提供してきた。
コノスルのブドウ畑では、殺虫、殺菌、除草のための薬剤散布をやめ、畝間に草花を生やし、合成肥料から堆肥へと施肥の仕方を変える取り組みが着々と進行した。ブドウの収穫が終わったら畑にたくさんのガチョウを放し、彼らに害虫駆除の仕事をしてもらった。土の中の微生物が戻り、畝間に咲く花を見つけて蝶や虫が帰ってきた。こうして、ブドウ樹を取り巻く生き物の繋がりが回復して、それがうまく循環するようになった。
そして、いまから10年近く前のこと、広大なサンタ・エリサ農園の真ん中を横断するように、ビオコリドー(生物の通り道)が設えられた。これは、この地がブドウ畑に変わる前に、ここに植わっていたであろう在来の草花や樹木を集めて植えた畑の中の緑地帯である。

サンタ・エリサ農園のビオコリドー
コノスルのブドウ畑の中でも、最近になって開拓した畑、カンポ・リンド(サン・アントニオ)やエル・エンカント(アコンカグア)の場合は、新しくブドウ樹を植えた時に、小川と在来の樹木をそのまま畑の中に残してビオコリドーとし、そこから近くの里山へと繋がる設計になっている。

カンポ・リンド(サンアントニオ・レイダヴァレー)のビオコリドー。ブドウ樹の区画を縫うように樹木と小川が走っている。乾燥のきつい今はドライ・クリークだが。

エル・エンカント(アコンカグア)のビオコリドー。サボテンなど乾燥に強い植物が自生している。
ブドウ畑のある風土の特徴を維持するためには、さまざまな虫や小動物など土地固有の野生生物が里山とブドウ畑を往来できる通路を確保する必要がある。さらに、ブドウの木の周りの生き物の好循環を、近くの里山や小川と結び付けることで、地域全体の生態系を守ることができる。ブドウ畑をブドウ樹の単一栽培ではなく多様な植物で構成された生態系に戻すことで、自然に害虫が除かれ、ブドウが成長するための栄養サイクルが完全なものになる。これは、ブドウ栽培に対する生態系の公益的機能といわれるものだ。冬の剪定でデザインし、夏の剪定で修正された樹列がどこまでも整然と並ぶようなブドウ樹だけで作られた景観は、もはや過去のものになりつつある。
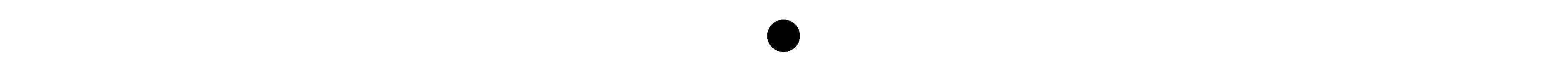
ブドウ樹の根の周り(根圏)の微生物の復帰と、新梢や葉の周り(葉圏)の整備から始まった有機栽培の取り組みは、ブドウ畑を含む地域全体の生態系の保全へと進展している。もはや、統合農法だ、有機農法だ、いやビオディナミ農法だと、ブドウ樹の周囲だけのことを言い争っている時ではないらしい。ブドウ畑を取り巻く全体の環境、その生態系を回復し保全しないといけない。
チリ大学・生態学生物多様性研究所は、「里山とそれに近接するブドウ畑のそれぞれに生息する微生物を調べると、菌類とバクテリアの80%は同じものでした。ところがブドウ畑が里山から遠ざかるにつれて、それぞれの菌類の群集が異なっていくのです。つまり微生物にも土地固有の風土性があり、里山とそれに近接する耕作地はひとつの生態系にあるのです」と、言っている。チリ中央部の里山は夏にはすっかり禿山だが、冬になると緑が盛り返す。乾燥地に強い生物がしっかり生きている。
また、この研究所の調べでは、「ブドウ畑の吸収できる二酸化炭素量は約5トン/haだが、森林のそれは24トン/haにものぼる」という。つまり、ブドウ樹の単作より多様な植物を栽培した方が全体的には二酸化炭素量を低減し、地球温暖化防止にも繋がるというわけだ(この件については、またの機会に)。
ブドウ樹の畝間に在来の草花を植えて虫や蝶を集め、堆肥を使用して地中の微生物をどんどん増やす。そして、ブドウ畑にはブドウ樹だけでなくさまざまな在来種の植物を植え、そこに野生生物の通路を作って里山へと繋げる。このようにブドウ畑を含む所有地全体の生物多様性を高めることは、ブドウ栽培の持続可能性を高めるだけでなく、ひいては気候変動の原因を軽減することに役立つ。コノスルはいま、自社所有のブドウ畑だけでなく契約栽培地にも生態系維持の取り組みを広げようと努めている。
この記事を書いた人

ばんしょう くにお
番匠 國男
ワインライター。ワインとスピリッツの業界専門誌「WANDS」の元編集長。ワインと洋酒の取材歴37年。「日本ソムリエ協会教本」のチリとアルゼンチンの項を執筆。1993年のコノスル創業以来、ほぼ毎年、コノスルのブドウ畑と醸造所を訪問している。フットボール観戦が趣味。週末は柏レイソルの追っかけ。海外取材の際も時間が合えばスタジアムへ出かける。