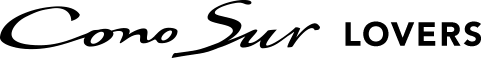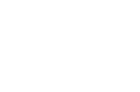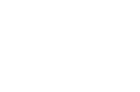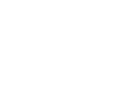2021.04.21
- チャリンコ通信
【チャリンコ通信】Vol.4 青いカルメネール、紅いカルメネール(前編)
紅葉するブドウ畑。収穫したブドウをチャリンコに載せて運ぶ人々。
4月も半ばを過ぎると、チリのブドウ畑のあちこちで、紅く色づいた葉の区画を目にするようになる。カルメネールだ。葉の紅色をカルミンCarmin(英語のクリムゾンCrimson)といい、そこからカルメネールという品種名になったと云われている。
同じ畑の他の区画に植わっているブドウ品種、たとえばメルローやカベルネ・ソーヴィニヨンは、秋になると黄色くなって落葉する。だから収穫期が近づけば、どこにカルメネールが植えてあるのかは素人目にも明らかだ。
今回は、そんなカルメネールにまつわるちょっと専門的な話。
●
カルメネールは、1994年にチリのブドウ畑で見つかった、とされている。それまでチリの栽培家がメルローだと思っていた樹の多くが実はカルメネールだったというわけだ。以来、「あろうことかチリのブドウ農家とワイナリーは、100年以上にわたってメルローとカルメネールが同じものだと考えていた」と云われるようになった。この指摘には「まぁ、なんと間抜けなこと」というニュアンスが含まれている(ように感じる)。
また、「(カルメネールは)チリ中のワイン産地に広がっていきましたが、そのプロセスでメルローとの混同が起こり、メルローと勘違いされて栽培が行われていました。1990年代初頭にブドウ学者によってメルローとの混植が発見され、カルメネールとしての栽培を実証したあと正式に認証されました」というカルメネール解説もある。いまではこういう見方が普通になっているのかもしれない。
けれども、チリの人々がメルローとカルメネールを混同したり、勘違いしたりしていたというのは事実ではない。秋になると素人目にもはっきりわかるカルメネールとメルローの違いを、ブドウ栽培家が、栽培のプロが、およそ4世代100年以上にわたって混同しっぱなしのはずがない。だから改めてカルメネール発見に至る事情を浚うことにした。

4月。色づくコルチャグア・ヴァレーのカルメネール
●
彼らはちゃんと知っていた。自分の畑に早生(わせ)のメルローと晩熟(おくて)のメルローがあることを。そして仲間内では晩熟のメルローを「メルロー・タルデ」とか「メルロー・チレノ」と呼んでいた。ただ、そのブドウの本当の名前を知らなかったし、知る必要もなかったのである。さらにカルメネールを知らなかったのはチリのブドウ畑で働く人だけではない。チリの醸造家もボルドーのシャトーも誰もがみな知らなかったのである。
知っていたのはフランス・モンペリエのジャン・ミッシェル・ブルシクオだった。アンペログラフィーAmpelography(ブドウ品種学)という学問があって、ブルシクオはその学者、ブドウ品種の研究者だ。彼は、19世紀のボルドーに「カルムネルCarmenère」というブドウ品種が存在していたことを知っていた。
1994年、サンティアゴで開かれた学会に招聘されたブルシクオは、その足でマイポやラペルのブドウ畑を見て回り、メルロー・タルデはかつてボルドーで栽培されていたカルムネルであると断じた。このとき初めて、メルロー・タルデの本名が人々に知らされたのである(チリの人々はその綴りを知ってカルメネール、カルメネーレと読んだ)。19世紀半ばまでボルドーに存在したとされるカルメネールが、20世紀末になってフランスから遠く離れたチリで見つかった。このブドウが100年以上ものあいだ、忘却の彼方に追いやられていたのはなぜか。それには二つの理由が考えられる。

一般にブドウの葉は黄色くなって落葉する
●
カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワール、シャルドネ。これはいずれもブドウ品種名だが、いまはワインの名前にもなってラベルに表示されている。ワインがブドウの名前で呼ばれるのは、いまでは至って当たり前のことだけれど、長い長いワインの歴史の上では、それはほんのつい最近のできごとだ。まだ50年と経っていない。それまでワインはエルミタージュ、マルゴー、ポマールのように産地名で呼ばれていた。そしてワインの消費地では、エルミタージュもマルゴーもポマールも、どんなブドウ品種で造られたのか誰も知らなかった。
1970年代になると、それまでシャブリ、ポートなどの名前を騙り贋作を造っていた米国やオーストラリアで、物真似でない産地独自のワインを造ろうという動きが生まれた。新しい生産者はラベルにシャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨンといったブドウ品種名を書き、それを「ヴァラエタルワイン」(ブドウ品種を英語でヴァラエティという)と名乗ることで、自らのワインが贋作シャブリとは違うこと、もっと高品質であることを主張したのだった。
このカリフォルニア発のヴァラエタルワインを、米国と世界の消費者が好んで受け容れたから、カベルネとシャルドネはすっかり有名になった。そして、カベルネとシャルドネは世界中のブドウ畑へ拡散していった。同時にカベルネ・ソーヴィニヨンはボルドーを、シャルドネはシャンパーニュとシャブリを造るブドウ品種であることも広く知れ渡った。こうして、ながらく「産地」の陰に隠れていた「品種」が、初めて「産地」をこえて表舞台に立ったわけだ。
カベルネ、シャルドネの大騒動のあと、それに飽きた消費者はカベルネ、シャルドネに代わる何かを探し始める。メルロー、ピノ・ノワール、シラーなどがその候補にのぼり、白品種ではソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・グリージョに注目が集まった。さらに、イタリアやスペインのように古くからワインを造っている生産地には、地域ごとに固有のブドウ品種がたくさんあって、それらも脚光を浴びることになる。そしていまでは、ワインのラベルにブドウ品種名を記載することが当たり前になってしまった。
ヴァラエタルワインの台頭でブドウ畑もすっかり様変わりした。
もともとブドウ畑にはいろんな品種がごちゃ混ぜに植えられていたのだが、品種ごとに畝や区画を分けてすっきり植え替えられた。そして、ごちゃ混ぜの品種をまとめて収穫して発酵させていたものが、それぞれの品種の熟期をみて適時に摘み、別々に醸造して小樽で熟成させたあとで、樽を寄せて混ぜてボトルに詰めるようになった。
●
ボルドー品種が初めてチリのブドウ畑に移植されたのは1851年のことである。その苗木を用立てたフランスの苗木商が誰だったのか、いろいろ調べてみたがまだ分からない。ただ、その26年後の1877年に、フランスから日本の三田育種場に届いた苗木はパリの苗木商ヴィルモランから買ったものだという。三田育種場の記録によると、ボルドーの苗木は「ボルドヲ・ノワアル」と「ボルドヲ・ブラン」と記録されている。赤ワイン用ブドウ、白ワイン用ブドウと書かれているだけで個々の品種名は不明。一方、ブルゴーニュの苗木は品種名が記載されている。この苗木商がボルドー品種に詳しくなかったからなのか、あるいは複数品種が混植されているボルドーはそれらをワインの色で十把一絡げにして販売するのが常だったのか(たぶん、これでしょう)、正確なところは分からない。
推測の域をでないけれど(いまのところ確認できる記録が見つからないので)、チリに渡ったボルドーの苗木もこのように「赤ワイン用」と「白ワイン用」の二つに纏められていて、個々の品種名は分からなかったのではないか。
それをそのままマイポの畑に植えた。害虫フィロキセラ(ブドウ根アブラムシ)のいないチリでは台木に接木する必要がないので、ブドウ樹の世代交代はムグロン(取り木法)で行った。だから、1980年代初め、チリにカベルネ・ソーヴィニヨンのブームがやってくるまで原始(19世紀半ば)の状態できちんと保存されていた。ヨーロッパのブドウ畑の変貌(後述します)に比べると奇跡的なできごとだ。
そしてこのごちゃまぜ品種畑でできたワインを、チリではずっと「ボルドー」と呼んでいた。それ以外のワインは、西語で“おらが国のブドウ”という意味の「パイス」(英語のカントリー)だった。ボルドー到来の300年も前に宣教師がスペインから持ち込んだリスタン・プリエト(パイスの本名。21世紀になってDNA分析で判明した)は、その頃にはすっかり“おらが国のブドウ=パイス”になっていた。
サンティアゴとその近郊に植えられた「ボルドー」は栽培規模が小さく単収も少ないので一握りの富裕層のためのワインだったが、一本の樹にたくさんの房を付け、その房も大きいパイスはずっと庶民の味方だった。
●
人々がカルメネールの名前を知らなかったもう一つの理由は、それが19世紀末にはすでに本家ボルドーで絶滅していたからだった。
このブドウは19世紀初めのボルドーでは最晩熟の品種で、天候に恵まれた年には色も濃く糖度も上がるけれど、そんな年は何度もやってこない。春先の気温が低いと花ぶるいをおこして実がスカスカの房になる。晩熟品種だから熟す前に雨や寒さがきてしまう。なんとも厄介なブドウだった。
19世紀後半、ボルドーのブドウ畑は北米から来た害虫フィロキセラ(ブドウ根アブラムシ)によって壊滅的な被害をうけた。復興を目指す人々は試行錯誤の末、フィロキセラ耐性のある北米原産種を台木にしてボルドー品種の穂木を接木するという解決策を見つけ、ボルドーは20世紀初めに再生した。その接木の際に穂木になる品種が選抜された。メルローやカベルネ・ソーヴィニヨンは優秀な成績で選抜試験をクリアしたが、元来、ボルドーに栽培適性のなかったカルムネルは落第してしまった。それからほぼ100年が経ち、カルムネルは原産地ボルドーでもすっかり忘れ去られていた。
ところがマイポの「ボルドー」はごちゃ混ぜ状態のまま、春先が温暖で晩秋まで乾燥した日の続く気候のもと、わが世の春を謳歌していた。1980年代初め、漸くチリにもカベルネ・ソーヴィニヨンの流行がやってきた。そうだ、「うちのボルドー」の中にもカベルネ・ソーヴィニヨンが混ざっているはずだ。このとき初めてチリの人々はカベルネ・ソーヴィニヨンが何かを知った。そしてそれをごちゃ混ぜ畑の中で捜してワインを造ったら大当たりした。遠く離れた日本でも「チリカベ」で沸いた。
続いてやってきたのはメルロー・ブーム。これも「うちのボルドー」の中にあるはず。いや待てよ。そのメルローというのは「メルロー・テンプラーノ(早熟)」のことか「メルロー・タルデ」のことか。大学で栽培学を修めたアグロノモに聞いたがわからない、ボルドーのコンサルタントに問いあわせたけれど誰も知らない。えい、ままよ! カベルネ以外はみなメルローだ。一緒に摘んでワインにしてしまえ。なんと、これが当たった。よく熟したテンプラーノと未熟で酸っぱさと青さの残るタルデが混ざることで、チリの「メルロー」は他にはない独特の複雑味を創りだしたのだった。
●
1990年代になって、漸くチリのブドウ畑にも新しい技術が導入された。それは、畑の畝に一本のホースを渡し、樹1本間隔に小さな穴をあけ、ホースに通した水をその穴から樹の根元にぽたぽたと点滴する灌漑方法である。ホースに通す水は近隣の川からポンプアップして送水される。
ここに至るまでチリのブドウ畑で起きた革新は、20世紀半ばにイタリア移民の教えたパラル(ペルゴラ)という大量生産のための棚作りだけだった。支柱を立て針金を渡して天蓋をつくり、そこに蔓を沿わせて伸ばす(日本のブドウ棚とほぼ同じものです)。用水路から灌漑水を引いて水田のようにザーッと流し込む。強粘土の水田とは違い、ここでは水がすぐに地中に浸み込んでいく。あっという間に単収の上がる大量生産に適したシステムだった。
しかしこれには初期投資が必要だ。用水路も引かねばならない。マウレやビオビオの小作農家にはできない相談だった。だから彼らは数百年前に宣教師の教えたスペイン由来のカベサ(株仕立て)を続けた。これなら非灌漑でやれるし、収量は少ないけれど自家用にはそれで十分だった。ところがいま、それが思いもよらぬ高評価を得ている。“ドライ・ファーミング”“オールドヴァイン”“パイス・ルネサンス”“VIGNO”。詳しいことは知らないが、大きなワイナリーが競ってうちのブドウを買いに来るようになった(この話はまた別の機会に)。

マウレ・カウケネスの株仕立てカリニャン
話が脱線した。つまり、点滴灌漑の導入を機に、チリのブドウ畑は畝や区画、時には一枚の畑をそっくり品種毎に植え分けられた。そして、フランスのブドウ品種学者に教えを請うたらメルロー・チレノはカルメネールだと分かったのである。
●
もういちど前掲のカルメネール解説を読んでみよう。お察しのとおり、この書き手の想定するブドウ畑は、品種毎にきれいに分類され、丹精した垣根の並ぶ現代のそれである。そして、ブドウ栽培者たるもの、自ら育てるブドウの名前ぐらいは知っているはずという前提に立っている。いまでは当たり前のことだ。
ボルドーから届いた時には品種毎に束ねられ、それぞれちゃんと名前が付いていたのに、マイポからラペルへ、マウレへ、ビオビオへと移植されるうちに(ほんとは全国に広がっていないけれど)誰かが伝達ゲームを間違えてしまった。こうして長らくチリでは「メルローとの混同」「メルローと勘違い」が続いた、と解説しているわけだ。
おわかり戴けただろうか。さて「勘違い」が解消されたところで、カルメネールはどんなブドウか、コノスルのカルメネールはどんなワインかという説明に移ろう、と思ったが紙幅が尽きた。続きは後編で。
この記事を書いた人

ばんしょう くにお
番匠 國男
ワインライター。ワインとスピリッツの業界専門誌「WANDS」の元編集長。ワインと洋酒の取材歴37年。「日本ソムリエ協会教本」のチリとアルゼンチンの項を執筆。1993年のコノスル創業以来、ほぼ毎年、コノスルのブドウ畑と醸造所を訪問している。フットボール観戦が趣味。週末は柏レイソルの追っかけ。海外取材の際も時間が合えばスタジアムへ出かける。